HUB-SBA MAGAZINE
基礎ワークショップの最終報告会イベントが行われました。
2019年01月12日
1月12日(土曜日)、経営管理プログラム基礎ワークショップの最終報告会が開催されました。このイベントでは、最も優れた成果を上げた各ワークショップ代表者によるプレゼンテーションが行われました。
今回は、在校生だけでなく、昨年秋に実施された試験に合格し、この4月から入学を予定している方々もお招きして、入学後の一橋ビジネススクールでの学びに触れていただく機会としました。
基礎ワークショップとは、春夏学期の導入ワークショップに引き続き、秋冬学期に開講される1年生全員必修の少人数授業です。ここでは学生各自の研究テーマをブラッシュアップし、それを解き明かすために必要な学術的方法論を学び、その成果として具体的な研究プロポーザル作成します。今回の最終報告会では、優れたプロポーザルが選ばれ、各ワークショップの代表者がその内容、発想、発表の冴えを競い合いました。
 |
|
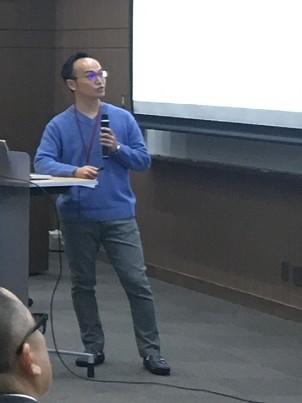 |
|
報告会では6人の代表の方々が登壇し、見事なプレゼンが行われました。続いて会場との間で活発な質疑応答が行われ、それぞれのワークショップでの普段の和気藹々とした議論を彷彿とさせる充実したディスカッションが繰り広げられました。
最終的に、教員団による厳正な審査の結果、以下のように受賞者が決まりました。
グレイト賞(最優秀賞)として、木野本朋哉さん「デジタル化を拒否する組織-デジタル化の推進を阻害する組織特徴に関する一考察」がその栄誉を得ました。現在、経営課題として最も重要視されているはずのデジタル化が、なぜ企業で思うように進まないのかという問題意識に基づいて、リクルートや日本経済新聞社を問題探索の対象にして、「ROI志向、顧客志向、ステークホルダーとの独立的関係が欠如する組織では、既存ビジネスへの固執が強くなるのではないか」という仮説が提示されました。あらゆる意味で、ぜひ続きが聞きたくなる素晴らしい発表でした。
ザッツ・インタレスティング賞(優秀発想賞)には、亀原栄二さん「企業の環境変化への適応プロセスについて-業種変更を行った企業に着目して」が選ばれました。「なぜ環境変化に適応し自己革新できる企業とできない企業があるのか、企業はどのようなプロセスで環境変化に適応するのか」という問題意識に基づいて、証券コード協議会で所属業種の見直しをした企業に着目し、それらに共通する組織能力を探索するという研究計画が発表されました。ユニークな着眼点に基づく対象選択や分析設定が高く評価されました。
ベスト・プレゼン賞(優秀発表賞)には、加藤怜子さん「事例研究:日立物流-日立物流がグループ外顧客を得て売上を高めていけたのはなぜか」が選ばれました。子会社が親会社への依存を脱却して外部に顧客を広げられた成功事例として、日立物流の社史をたどり、同社が当初、グループ内の仕事から汎用的・包括的な物流ノウハウを蓄積しつつ、それをグループ外に展開し、そこでさらに蓄積を進めていったプロセスが明らかにされました。堂々とした明快な発表で、聴衆への説得力が抜群でした。
その他の代表者の報告も、独自の視角に基づいた問題設定と、ビジネスや社会問題解決に向けて聴衆の好奇心を喚起する内容にあふれ、いずれも劣らぬたいへん素晴らしいものでした。
イベント後半には、2年次ワークショップ(=主ワークショップ)のショーケースセッションが行われました。2年生になると、主ワークショップに所属し、基礎ワークショップ
一橋ビジネススクールの最大の特徴は、受講生が自分の関心に従った問題を自分で設定し、教員と受講生が一緒になって問いを深めていくことにあります。こうした2年間続く少人数でのワークショップ(1年次前半の導入WS、1年次後半の基礎WS、2年次の主WS)によって、経営に関する深い思考力が培われていきます。2年次にも、引き続き学生の皆様のさらに充実した学びを期待しております。
基礎ワークショップ最終報告会
発表者および発表タイトル
| Aクラス | 亀原栄二さん | 「企業の環境変化への適応プロセスについて-業種変更を行った企業に着目して」 |
| Bクラス | 加藤怜子さん | 「事例研究:日立物流-日立物流がグループ外顧客を得て売上を高めていけたのはなぜか」 |
| Cクラス | 木野本朋哉さん | 「デジタル化を拒否する組織-デジタル化の推進を阻害する組織特徴に関する一考察」 |
| Dクラス | 岩波竜太郎さん | 「粉飾決算を防ぐためには」 |
| Eクラス | 阿部健太郎さん | 「介護施設における人事・組織マネジメントにより、介護業界の人手不足は解消され、事業収入は増加するか」 |
| Fクラス | 山口章宏さん | 「無形財サービスの提供を主とする業態において、本業を通じた社会貢献を強調した市場とのコミュニケーションは、購買意向にどのような影響を与えるか」 |